【国が認めた水産品】 GI保護制度 登録水産品まとめ
GI保護制度とは?
実はここで説明しなくても、最初の前振りのところで説明が完了しています笑
その内容を簡単にまとめると、”ホンモノのブランド品をニセモノから守る制度” です。
さらに詳しい説明として、辞書に書かれている内容をご紹介します。
農産物の優れた品質や社会的評価が、地理的な気候や風土、歴史などに由来する特徴として原産地と関連づけられる場合、知的財産としてその名称を保護する制度。地理的表示とは単なる産地名ではなく、生産地として長年培われてきた品質と信頼、産地の特徴を示すもので、これを表示することによって他との差別化をはかることができたり、価格や輸出などの面でプラスの効果が期待できる。2014年(平成26)6月に成立した「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」(平成26年法律第84号)に基づき、翌2015年6月から運用が開始された。略称はGIで、地理的表示制度ともいう。
コトバンク 日本大百科全書 「地理的表示保護制度」の解説
「知的財産」として保護するという点が、これまでそのブランド品に関わってきた方々を尊重しているようで良い内容であると私は思いました。
このGI保護制度には、2015年6月から開始して以来、2022年6月時点では41都道府県の116産品と2か国(イタリア、ベトナム)の3産品の計119産品が登録されています。
この中で水産品は14産品が登録されています。
次にその14種類について、簡単にご紹介していきたいと思います。
GI保護制度登録水産品一覧

それでは、「GI保護制度」に登録されている水産品について、登録された順にご紹介していきます。
下関ふく(山口県 2016年10月)

下関ふくは水産品初のGI登録産品です。
明治時代に伊藤博文がふぐ食を推奨したことをきっかけとして、下関は一躍ふぐの街として有名になりました。
下関ふくとは特に、下関市の南風泊市場で水揚げされ、毒処理である身欠き処理をされたトラフグのことをいいます。
南風泊(はえどまり)市場はトラフグ取扱量日本1位を誇る市場です。
また、「ふぐ」では「ふく」であることに違和感を感じた人がいるのではないでしょうか?
山口県ではふぐを「福」として縁起を担ぐ伝統があり、そこから「ふく」という呼び名が来ていると考えられています。
(参考:協同組合 下関ふく連盟、山口県 地域団体商標登録一覧 下関ふく、ふぐの豆知識 山口でふぐのこと『ふく』と呼ぶわけ)
十三湖産大和しじみ(青森県 2016年12月)

十三湖は津軽半島の北西部に位置する湖であり、白神山地から注ぐ岩木川と日本海が交わる汽水域となっています。
この環境は大和しじみにとって最高の生育環境であり、そこで成長した大和しじみからは旨味が良く出た出汁がとれるようです。
また、十三湖での大和しじみ漁は、漁の時期や1日当たりの漁獲量などといった詳しいルールが決められており、これによって品質の高い大和しじみの持続的な生産が実現されています。
(参考:青森のうまいものたち 十三湖のシジミ)
みやぎサーモン(宮城県 2017年5月)
みやぎサーモンの種類は銀ざけと呼ばれる種類です。
特徴としては、水揚げ後すぐに「活け締め」や「神経締め」と呼ばれる鮮度を維持するための処理が施されることで、新鮮で刺身でも食べられる高品質なサケとなっています。
宮城県の海岸はリアス式海岸であるために水深が深く波も穏やかである、かつ海水温が7月後半まで20℃以下と低めである、という銀ざけの養殖に適した環境となっており、これらの理由もあって宮城県が銀ざけ養殖の発祥地となりました。
現在では日本一の生産量を誇っています。
(参考:みやぎサーモン、PRIDE FISH 宮城県 みやぎサーモン)
田子の浦しらす(静岡県 2017年6月)
田子の浦しらすの漁場は、富士山や南アルプスの山々からの栄養によってプランクトンが豊富にある駿河湾の最北部に位置し、また水揚げ港までの距離が短いという特徴があります。
さらに、しらすを傷つけることなく漁獲できる「しらす一艘曳網量(引き網漁)」による漁獲や、船上での氷締めなどの作業を徹底することで、鮮度良く形のいいしらすが水揚げされています。
これまでは生のしらすがGI登録されていましたが、2021年4月から「釜揚げしらす」も追加で登録されました。
(参考:田子の浦漁業協同組合)
若狭小浜小鯛ささ漬(福井県 2017年11月)
福井県に面する若狭湾で、漁業技術の発展によって、「レンコダイ(キダイ)」というマダイよりも色鮮やかで身や皮が柔らかいという特徴を持つタイが大量に漁獲されるようになりました。
そのレンコダイの使い道として開発されたのが、この若狭小浜小鯛ささ漬です。
作り方としては、日本海産の小鯛(レンコダイ)を三枚におろして、振り塩または塩水に漬けて塩分を浸透させ、酢あるいは調味酢に漬けた後に、一定量を樽詰めする、という製造工程が取られています。
(参考:小浜ささ漬協会)
岩手野田村荒海ホタテ(岩手県 2017年11月)
岩手県の野田村では、「野田式外海流育法」という独自の養殖方法が取られています。
具体的には、一般的なホタテの養殖は内海で行われるが、あえて荒波の外海で育てることで、身が肉厚で旨味が濃く、貝柱は繊維がしっかりしていて弾力のあるホタテとなっています。
さらに、外海では生活雑排水の影響を受けないため、キレイなホタテを生産することができるというメリットもあるようです。
(参考:岩手野田村荒波ホタテ、ととけん副読本 2021年版)
小川原湖産大和しじみ(青森県 2017年12月)
青森では十三湖産大和しじみに続く2つ目の大和しじみのGI登録品です。
小河原湖は東北最大の汽水湖であり、水質や底質が大和しじみの生息環境として良好となっています。
小河原湖での大和しじみ漁では、エンジン動力を用いた船を使用して漁具を曳いて漁獲するという方法が取られていないため、漁獲時に大和しじみに与えられるダメージは小さく、貝殻を傷つけたり弱らせたりすることが避けられます。
よって、外見も良く、出荷後も鮮度の良い状態を維持できるというわけです。
また、4年かけて成長させてから漁獲するため、殻長が最低でも15 mm 以上の大粒の大和しじみが保証されています。
さらに、しじみ専用の市場を設けることで、小川原湖で漁獲された大和しじみを一括で管理することができ、これによって品質にばらつきがなく安定した供給を行うことが可能となっています。
越前がに(福井県 2018年9月)

越前ガニとは、福井県で水揚げされたオスのズワイガニのことを指し、黄色いタグが付けられているのが特徴です。
また、90年以上にわたり皇室に特産品として献上されているという歴史を持つ、唯一の皇室献上ガニとなっています。
福井県にある越前海岸沿岸は、
「急深で、ズワイガニの生息水域である水深250~400 m まで一気に深くなっており、そのため短い時間で漁場を行き来できる」
「漁場の地形が段々になっており、ズワイガニにとって生息しやすい地形となっている」
「暖流と寒流がぶつかる漁場であるため、ズワイガニのエサが豊富である」
という、ズワイガニの好漁場の条件が重なっていた結果、日本で一番有名な産地となることができたようです。
(参考:えちぜん観光ナビ 越前がにのまち越前町)
豊島タチウオ(広島県 2019年9月)
豊島タチウオの漁場である豊島沖は、緩急の富んだ潮の流れによって、タチウオのエサとなるイカナゴなどの小魚が集まる好漁場となっています。
このタチウオを豊島の漁師に代々受け継がれてきた釣り漁法によって漁獲し、魚体に触れないよう注意しながら、船上にて選別して直ちに氷締めすることで、傷のない美しい外観と高い鮮度を有した状態で出荷することが可能となっています。
田浦銀太刀(熊本県 2019年12月)

田浦銀太刀は、肉付きが良く、脂がのる割に白身魚の旨味も備わっており、また光沢のある鮮やかな銀白色の美しい外観をしていることが特徴となっています。
熊本県に面する八代海は九州本土と天草諸島によって囲まれた閉鎖性の高い内海で、球磨川から運ばれる栄養分によってイワシ等の小魚が豊富であることから、八代海のタチウオは周年を通して豊富なエサを摂取でき、これによって身の質が良くなっているようです。
田浦地区はこの八代海におけるタチウオの回遊経路の中心に位置しているため、地理的に漁場探索に有利な釣り漁法が定着したことにより、傷の無い綺麗な状態での出荷が可能となっているようです。
(参考:地理的表示産品情報発信サイト 田浦銀太刀)
大野あさり(広島県 2019年12月)

大野あさりはほとんどが殻長35 mm 以上と大粒で、身質は肉厚でふっくらとし、味は濃いという特徴があります。
大野あさりの漁場である大野瀬戸には、宮島の豊かな森林からの河川水や伏流水が流れ込んでおり、餌となる植物プランクトンやあさりの殻形成に必要なミネラルが豊富に含まれているため、あさりが良好に成長することができます。
大野あさりの漁獲は、干潟の漁場を漁業者ごとに区割りして管理させる「区割り漁法」によって行われているため、あさりを大型に成長させてから出荷することが可能となっています。
(参考:浜毛保漁業協同組合 大野あさりとは、ととけん副読本 2021年版)
檜山海参(北海道 2020年3月)

「海参」と書いて「はいしぇん」と読みます。
日本語では「いりこ」と読み、ナマコの腸を取り除き、塩水で煮てから干したもののことを言います。
生産地の沿岸地域は岩礁帯が多く、適度に砂地もあるため、なまこの生息に良好な環境となっており、イボが多く、干しなまこの原料として良質ななまこが漁獲されます。
特に檜山産はイボの数が多く、イボ立ちもいいことから北海道において最高値で取引されているようです。
(参考:檜山振興局 檜山海参、ととけん副読本 2021年版)
網走湖産しじみ貝(北海道 2020年12月)
網走湖産しじみ貝とは、網走の冷涼な気候で約7年以上かけて育った大粒のヤマトシジミのことを言います。
網走湖は冷涼な気候であるため、成長が遅いと言われ、天然の旨味成分を湖底でしっかり蓄えて成長することで、他の産地よりも身がプリプリしていて味も良いシジミになるようです。
網走湖では年間および日産漁獲量が定めることでヤマトシジミの資源管理がされており、また鮮度を保つために早朝に出港して気温が上がる前に漁を終えるという工夫がなされているようです。
(参考:おおぞら三昧株式会社 網走湖産大和しじみ~商品開発への道~、ととけん副読本 2021年版)
広田湾産イシカゲ貝(岩手県 2022年2月)

イシカゲ貝はきれいなクリーム色の身を持つ大きめの二枚貝であり、広田湾が国内で唯一の養殖産地となっていることから「幻の貝」と呼ばれています。
漁場である広田湾は、「清流気仙川を通じて山からの栄養分が流れ込む内湾」と「親潮由来の栄養分と黒潮由来の栄養分が混ざり合う外湾」を有する恵まれた環境となっています。
広田湾でのイシカゲ貝の養殖の歴史は長く、平成7年から養殖技術の確立を目指して環境整備や技術開発に取り組んでいるようです。
(参考:陸前高田市 広田湾産イシカゲ貝)
最後に

ここまでお読みいただきありがとうございました!
今回は「GI保護制度」に登録されている水産物について、簡単にですがご紹介しました。
皆さまはいくつ食べたことがありますか?
今回使用した写真は全て関連するサイトから引用させていただきましたが、
いつか私自身が実際にこれらの水産品を購入してみて、撮った写真を追加していきたいと考えています。
その際はまた報告します😊
それではまた次回のブログでお会いしましょう!
お疲れ様でした~😄
2022.06.27 うぉーらる









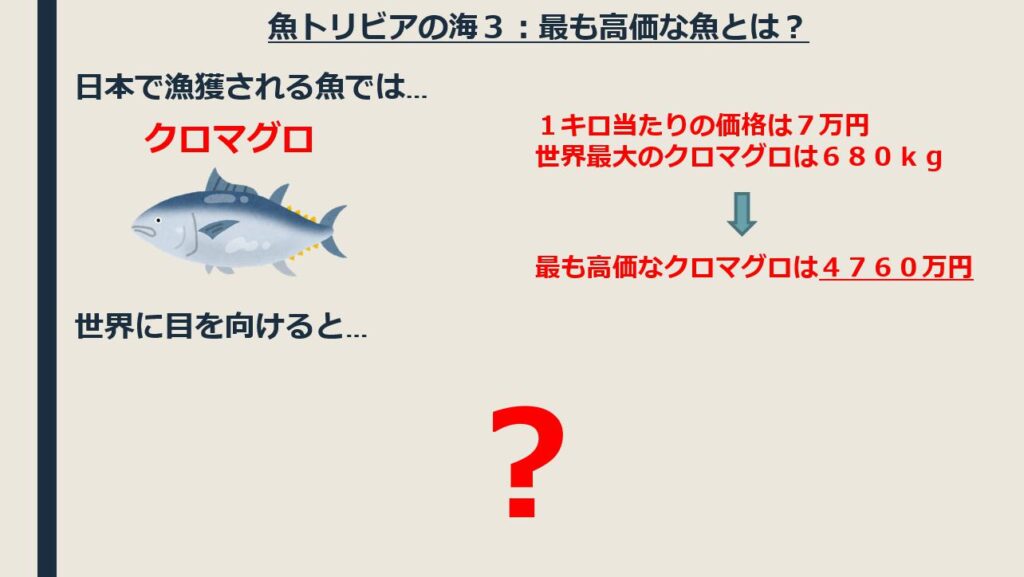
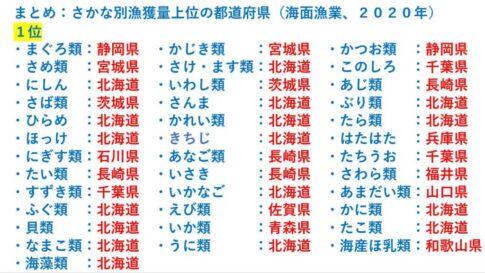
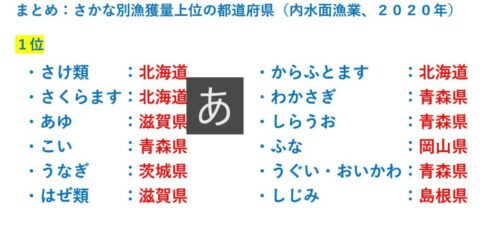
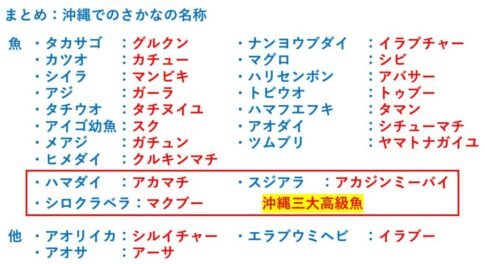



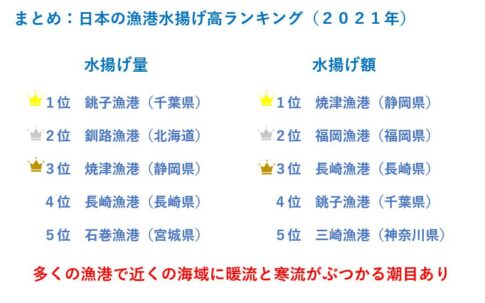

当ブログにお越しいただきありがとうございます!
管理人のうぉーらるです。
皆さまは「GI(Geographical Indications:地理的表示)保護制度」というものをご存じでしょうか?
日本で一番有名な肉であるといっても過言ではない神戸ビーフなど、日本の各都道府県にはその土地を代表とするブランド製品が存在します。(魚のブログにも関わらずお肉を例に挙げましたが、後で水産品を全てご紹介するのでお許しください笑)
こういったブランドものには、残念なことに「ニセモノ」が多く現れることとなります。
当然「ニセモノ」の方が値段が安く設定されているため、「ホンモノ」が売れなくなるという最悪の事態が起こります。
この事態を防止するための制度が「GI保護制度」です。
今回はこの「GI保護制度」について説明していきます。